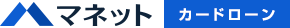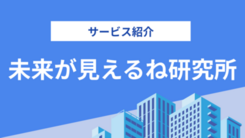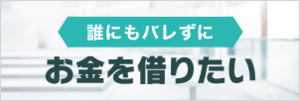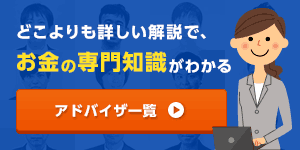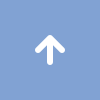企業型確定拠出年金は使ってる?メリットや仕組みを分かりやすく解説
【コンテンツの広告表記に関して】
>提携企業一覧
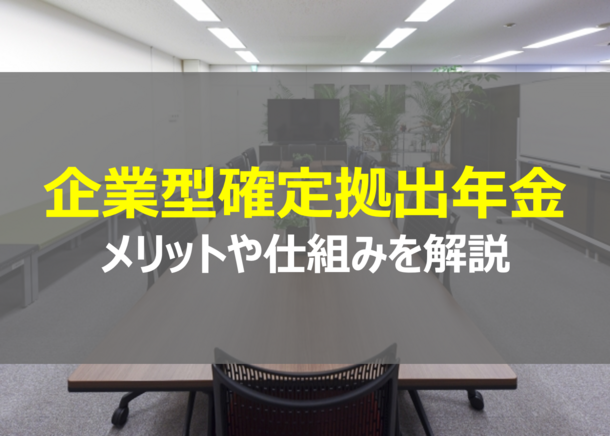
ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー(CFP認定)ファイナンシャルプランニング1級技能士、証券外務員一種、住宅ローンアドバイザー、DCアドバイザー。
1997年、まだ取得者の少ないファイナンシャルプランナー資格を知り、28歳の時AFP、30歳の時上級資格であるCFPに合格。会社員の傍ら、「金融機関に勤めたことのないファイナンシャルプランナー」として活躍。その後、「学歴も資格のひとつ」と思い、大検(現:高認)の学習を始め、10カ月後合格。短大入学後、大学に編入し、大学卒業資格を得る。その後、投資信託専門店舗、大手国内保険会社に勤務。現在は、取得した数々の資格を活かし、確定拠出年金やライフプランセミナー講師として活躍。個別相談では相談者が相談者を呼んでくる「わかりやすい説明」が評判を呼んでいる。
会社の制度だけどわからない
近年、確定拠出年金が話題になっています。自分の会社にも確定拠出年金制度はあるけど、内容はわからないという方も少なくありません。そこで「会社の制度だけど、いまさら聞けない」という方に、確定拠出年金制度についてお伝えしたいと思います。
そもそも何のための制度か
確定拠出年金は老後資金準備のための制度です。会社で採用する理由は、老後、つまり退職後のお金ということで退職金制度を担っています。
ただ、確定拠出年金は退職金制度なのに、「自分で資金を運用し、将来受け取る」という少々理解しがたい制度です。そのため、多くの方が複雑でわかりにくいと思われています。
確定拠出年金には専用口座がある
会社がお一人お一人に、老後資金積み立て専用口座を作ってくれています。その口座の中に、会社が毎月「掛金」という名のお金を入金してくれているのです。このことを掛金の「拠出」といいます。
掛金の出どころは、
とそれぞれの会社規約によって異なります。
「そんな口座は会社にはありません」と思う方はぜひ確認してみてください。
年に1回もしくは2回、直接ご自宅にまたは会社経由で手紙が届いていませんか。その手紙がこの口座の中身、つまり通帳の代わりなのです。
この退職金制度は自分で現状確認できます。手紙だけではなく、webサイトやコールセンターからも確認できるのです。
誰が運用しているのか
確定拠出年金はみなさんそれぞれが運用しています。制度に加入したとき、運用するための商品を選んだと思います。運用するつもりはなくても、毎月の掛金で選んだ商品を購入しています。
商品には、コツコツ積み立てるものや日々値動きするものなど、商品ラインナップの中から1つもしくは複数の商品を利用して、将来のために掛金を運用していきます。一度選んだ商品は、いつでも自由に変更することができます。どの商品をどんな割合で運用をするのかによって、将来の受け取り額に差が出るのです。
60歳以降、受け取り可能
老後資金のための制度ですから、60歳より前に受け取ることは原則できません。ただし、60歳になったら受け取るのではなく、60歳以降70歳までの間に受け取りを開始するのです。
受け取り方は、一時金、年金、一時金と年金の組み合わせ、年金で受け取る場合は、何年で年何回に分けて(規約により受け取り方の選択方法は異なる)受け取るのかを決めることができます。
将来、60歳以降も働いてその後もらい始める、公的年金を受け取るまでのつなぎとして活用する、一時金でもらって住宅ローンの残債を一括返済に充てるなど、その時の状況に合わせて選択できます。どのように受け取るかは、受け取るときに決めればいいのです。
確定拠出年金は何がいいのか
掛金には税金がかからない
確定拠出年金の最大のメリットは、税金の負担軽減効果でしょう。
通常、会社員の方は給料や賞与を受け取るときに税金を引かれた後の金額を、貯蓄や投資に回します。一方、確定拠出年金は掛金に対する課税はありません。つまり、税金を引かれない金額がこの口座に積み上がっていくのです。
所得税の速算表(平成27年分以降)
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
【参照】国税庁のホームページ
例えば、給料のうち課税される部分の金額である課税所得金額が300万円の方なら、所得税の税率は10%、10,000円に対する所得税は1,000円で銀行口座に振込される額(手取り)は9,000円となります。
一方、確定拠出年金の口座の中には10,000円のまま積み上がります。1年後には銀行の口座には108,000円入金されることになりますが、確定拠出年金の口座には120,000円お金が入ってきます。その差は12,000円。今、定期預金に1年間お金を預けても数十円から数百円しか利息は付きません。だったら、税金を差し引かれないで手元にお金を多く残すのも大事なことです。
会社員の方は、税金を自分で計算する機会が少ないので、気づかなかったという方も多いのですが、「老後のお金を準備しながら、現役時代の税金負担を軽くする」こともできていたのです。
税金は所得税だけでなく、住民税もあります。先ほどの課税所得金額が300万円の人なら、さらに12,000円の税金負担が軽くなります。
税金面でメリットがあることを「税制優遇」といいますが、税制優遇はまだあります。
増えても税金が引かれない
口座に入ったお金は運用されます。一般的に、お金は増えると利息や運用益から20.315%税金を差し引かれ、残りの金額を受け取ります。もし1年で10,000円増やしたら、税金を差し引かれ受け取り額は8,000円を下回るということです。
しかし、確定拠出年金の口座内で増やしたお金には税金がかかりません。10,000円増やしたら10,000円そのまま受け取ることができます。毎年わずかでもお金が増えるとしたら、受け取り終了までの長い期間に得られるメリットは年々大きくなります。
受け取り時にもメリット
掛金や運用益には税金がかかりませんが、受け取り時は課税対象です。ただし、60歳以降の受け取り、つまり仕事を定年退職等した人に大きな税金を課すのはおかしな話です。そのため、受け取り時には税金を計算する際、「控除」といって一定の金額に対して税金がかからないようにしています。
例えば、確定拠出年金に30年間掛金を拠出していた人が一時金での受け取りを選択した場合には、「退職所得控除」というものが適用され1,500万円までの金額に税金はかかりません。
また、年金受け取りを選択した場合には、「公的年金等控除」といって確定拠出年金の受け取りには大きな税金がかからないことになっています。
運用よりも税制優遇は大きなメリット
確定拠出年金で一番難しいのは「運用」といわれていますが、プロでも運用してコンスタントに運用益を得るのは難しいことです。
その点、確定拠出年金は税制優遇があることから、運用よりも確実に手元にお金を残す方法でもあります。
このほか、「会社掛金には社会保険料がかからない」「口座維持管理手数料等を会社が一部負担してくれている」「運用することで物価の上昇に負けない」などさまざまなメリットもあります。
知らないままではもったいないこの制度、ぜひ一度確認して活用してみませんか。