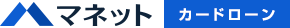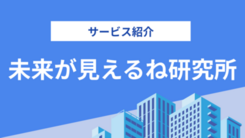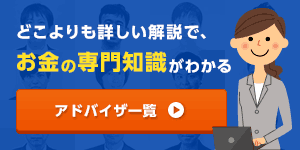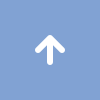子どもに迷惑をかけたくない!「教育費」を確実に貯める方法
∨【コンテンツの広告表記に関して】
>提携企業一覧
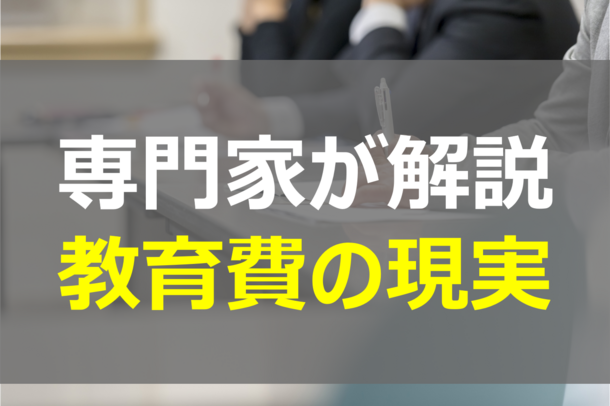
ファイナンシャルプランナー
大分県出身 九州大学教育学部卒
損害保険会社の営業事務等を経て、FPとして独立。家計相談を主に、セミナー、メディア出演等を行う。 自分自身のお金オンチな経験をいかして、世の中の変化が家計にどう影響するかを分かりやすく伝えることを 心がけている。プライベートでは小学生・保育園児の三姉妹の母。公式ページ「FP事務所シナリオ」
目標額を決めましょう
教育費は「金額が大きい」「タイミングをずらせない」という特徴があります。住宅費のように「家を買うタイミングを2年ずらして頭金を多めに貯められたら、より希望にあった家を買えるよね。」ということが、教育費ではできません。「決まったタイミングで確実に貯める」ことが求められます。
そのためには、まず「目標額」を決めることです。最も費用がかかる「大学費用」「大学への入学費」「仕送り」を参考に目標設定してみましょう。
大学の年間学校教育費(A)
 大学の年間学校教育費(A)
大学の年間学校教育費(A)
- 私立短大 140.5万円
- 国公立大学 98.2万円
- 私立大学文系 147.9万円
- 私立大学理系 178.4万円
受験費用・学校納付金・入学しなかった学校への納付金(B)
 受験費用・学校納付金・入学しなかった学校への納付金(B)
受験費用・学校納付金・入学しなかった学校への納付金(B)
- 私立短大 66.9万円
- 国公立大学 71.4万円
- 私立大学文系 86.6万円
- 私立大学理系 84.5万円
自宅外通学を始めるための費用(C)
- 自宅外通学を始めるための費用 平均39.1万円
自宅外通学者への年間仕送り額(D)
- 自宅外通学者への年間仕送り額 平均102.3万円(月額8.5万円)
(いずれも、日本政策金融公庫 令和元年度「教育費負担の実態調査結果」より引用)
目標額の計算
それでは、目標額を計算してみましょう。
大学の年間学校教育費(A)×4年(短大の場合は2年)
+受験費用・学校納付金・入学しなかった学校への納付金(B)
+自宅外通学を始めるための費用(C)
+自宅外通学者への年間仕送り額(D) ×4年(短大の場合は2年)
=目標額
となります。 例えば、「県外の国公立大学」を目標額にする場合は、
大学の年間学校教育費(A)98.2万円×4年(短大の場合は2年)
+受験費用・学校納付金・入学しなかった学校への納付金(B)71.4万円
+自宅外通学を始めるための費用(C)39.1万円
+自宅外通学者への年間仕送り額(D) 102.3万円×4年(短大の場合は2年)
=目標額 912.5万円
となります。自宅から通える大学にするのであれば、仕送りに関わる費用である(C)と(D)は不要になりますし、地方の大学であれば、学費は平均より低くなるかもしれません。
ペース配分を決めましょう
貯め時を見極めましょう
目標額を計算すると、「できるだけ早く貯め始めたい」となるのが教育費です。ただ、教育費の貯め方で失敗しがちなのは「貯め始めから貯め終わりまで、一定の金額で貯めるプラン」にしてしまうことです。
お子さまが小学生と高校生では、小学生の時の方が教育費の負担が少ないため、貯めやすいでしょう。しかし、小学生の時より高校生の時の方が親の収入が多ければ、高校生の時の方が貯蓄できるかもしれません。以前は保育園代が負担になっている家庭が多かったのですが、保育料無償化により、年少から年長の3年間に貯めやすくなりました。
教育費の貯め始めから教育費の貯め終わりの収入と支出のシミュレーションを作成し、教育費を貯めるのにがんばる「貯め時」と、そうではない時期とで、教育費の積立目標額を変えておくと家計への負担も軽減できます。
「児童手当」は心強い教育資金
大学の費用を貯めたくても、保育園や幼稚園代、学校の給食費、習い事の費用等、リアルタイムで必要な教育費もあります。そのような時に心強い存在は「児童手当」です。
0歳から中学校卒業までの児童手当の総額は約200万円にもなります。所得制限に引っかかる場合でも、総額は約90万円です。「児童手当は、いつの間にか生活費に使ってしまった」という声を良く聞きますが、できるだけ早く、将来の教育費として貯めるようにしましょう。児童手当を受け取る銀行口座を教育費専用にすると、生活費に使わずにすみます。
教育費の準備方法(金融商品)
教育費の目標額、貯めるペース配分を決めたら、いよいよ貯める方法(金融商品)について考えてみましょう。
積立預金
シンプルに銀行等の「積立預金」という手段です。「毎月の給料から、いつの間にか自動的に積立をする仕組み」を上手に利用しましょう。お勤め先の財形や社内預金があれば、ぜひ利用しましょう。その際に「教育費が必要なタイミングで引出が自由にできるか」を確認しておくと安心です。
学資保険
教育費の準備手段として王道だった学資保険ですが、低金利の影響を受け「学資保険に入っていれば、大学のお金も安心」という時代ではなくなってしまいました。学資保険を販売している保険会社も以前より少なくなっています。
契約者である保護者に万が一(死亡、高度障害)があった場合は、保険料の払込が免除され、満期になると予定通りのお金が受け取れるのは学資保険ならではです。加入を検討している学資保険が該当するか確認しておくと安心です。
中学・高校の進学時に祝金が出たり、子どもの医療保障等が付帯されている学資保険もありますが、その分、大学入学時の受取金の返戻率(受取額/払込額)が下がる場合がありますので、商品設計には注意しましょう。
また、返戻率をより高くするために、保険料の払込期間を短く設定する学資保険が増えていますが、「保険料の支払いが負担になっている」という相談が少なくありません。やむを得ず途中で解約する場合は、元本割れになるかもしれません。「払込が継続できる保険料」で商品設計してもらうようにしましょう。
積立預金と同じく「いつの間にか教育費が貯まっている」仕組みですので、教育費の一部を準備する方法としては心強い存在です。
終身保険
学資保険の返戻率が、以前に比べて低くなっているため、より金利の高い終身保険を学資保険代わりにするケースが増えています。教育費が必要なタイミングで、途中解約する想定です。
より高金利を求めて外貨建ての商品を選択する人も増えていますが、解約時に為替が円高になっていると、受け取る金額が想定より少なくなる可能性(為替リスク)があります。また、保険料も外貨建てにする場合は、保険料も為替の影響を受けますので、「想定している保険料よりも高くなっている(低くなっている)」ということが起こりえます。
低解約返戻金型終身保険を利用する方も増えています。保険料払込期間中(教育費を想定する場合は、大学入学前まで)に途中解約した際の返戻率が低く設定されており、払込期間を過ぎて解約すると、払込保険料より多く解約金が受け取れる保険です。他の終身保険よりも保険料が割安のため、保険料の支払いが厳しくなることによって解約するリスクを減らせます。ただ、想定より早く解約すると、払込保険料よりも解約金が少なくなることを覚えておきましょう。
つみたてNISA
資産運用で教育費を貯める場合は、「つみたてNISA」を上手に利用しましょう。「つみたてNISA」は積立投資専用の「NISA(少額投資非課税制度)」で、年間40万円までの投資で得られた売却益、分配金に対して、最長20年間非課税です。金融庁による一定の資産基準をクリアした投資信託から選びますので、資産運用初心者でも始めやすいのが特徴です。
注意点は売却するタイミングです。子どもが大学に入る直前など換金のタイミングで、投資信託の価格が下がっている可能性があります。あらかじめ決めた目標額が確保できたら、必要なタイミングよりも前に売却するという決断も必要になるでしょう。
奨学金
奨学金の利用を検討するのも選択肢の一つです。奨学金利用者は増加傾向にあり、現在、私立大学に通う学生の2人に1人が利用しています。ただ、奨学金の利用を決める際は返済計画について、どこまで親がサポートして、どこから自力で本人が返済するか等を必ず親子で話し合った方が良いでしょう。
実際に必要になる額はよくよく考えて算出を
子どもの教育費といっても、居住地域や通う学校によって大きく異なります。子供の成長によって様々なパターンが考えられますので、そのあたりも含めて複数の費用シミュレーションを考えておく必要があります。
このあたりの具体的な金額については、下記の記事などで非常に詳しく解説されていますので、参考になるかと思います。
教育費は中長期によって必要になるお金で、子供の人生を大きく左右しますので、慎重に考えて後悔のないプランを想定しましょう。
まとめ
住宅費、老後生活費と並ぶ、人生三大支出の一つが「教育費」です。高校3年生までは、できるだけその年の収入の範囲内でやりくりをし、受験~大学卒業までのお金は前もって貯めるようにしましょう。
各金融商品にはメリット、デメリットがありますから、いくつかの金融商品を上手に組み合わせて、できるだけ早く貯め始めるのがコツです。